532 天命昇華
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新

南極石の王子 クレステッド
― かつての話 ―
[故国リュゲナー王国が失われたのは、10年も前の話だ。
国王に不満を抱いた王弟が隣国の地方領主と手を結び、王宮を攻め落とした。
国王は護衛と共に城を脱出したが、王子である自分は別の方向へと逃がされた。
リュゲナーの血を絶やすなという言葉が耳に残っている。
王の隣には、自分の身代わりに乳兄弟が付き添っていた。
それこそ兄弟同然に育った相手だ。
父と別れるよりも辛かったが、彼にしか自分の身代わりは務まらないのは確かだった。]
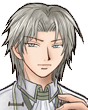
南極石の王子 クレステッド
[混乱の中、少数の護衛と共に街を脱出した。
その後、別の国へと逃れてしばらく身を潜める予定であった。
だが国境を超えるより先に追っ手に見つかった。
こちらへ追討隊が出たということは、王と乳兄弟はもう……。
眼前が暗くなる思いだったが、状況はそんな余裕を許さなかった。
追討隊と護衛たちの間で戦闘があり、自らも剣を抜いて立ち向かった。
だが多勢に無勢。護衛はすべて斬り伏せられ、自らは剣を叩き落されて追い詰められた、絶体絶命のその時、傍らの森から黒い霧のようなものが湧き出して、―――意識を失ったのだ。]

南極石の王子 クレステッド
[それからどうなったのかはよくわからない。
ただ、自分を助けたのは、迷いの森と呼ばれるこの森の主であるらしかった。
ここにいる限り安全だと彼は言ったが、外に出してはくれなかった。
父王が処刑されたことと、故国が隣国の一部になったことは教えてくれたが、詳しい様子は聞かされなかった。
父の仇を取りたい、国を取り戻したいと願っても、まだ早いと諭されるばかりだった。
知識を蓄え体を鍛え武を磨き、来るべき時に備えていたある日、森の中に迷い込んできた商人から初めて故国の様子を聞いたのだ。
曰く、悪政によって民は疲弊し、街は乱れる一方であると。]
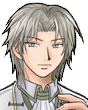
南極石の王子 クレステッド
[保護した商人を伴って森の主の館へ戻り、国へ帰りたいと願った。
彼は沈黙の後、一つの伝承を語った。
曰く、『神魔の領域』に赴き、『試練』を超えれば、願いが叶うと。
国を取り戻すための力も兵も貸せないが、試練に挑む手助けはしよう、と。
かくして旅に必要なものを与えられ、良き日を選んで送り出されたのだった。]
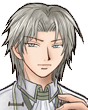
南極石の王子 クレステッド
[道中、特に問題などはなかった。
守りの術のおかげか、正体に気づかれることもなかった。
途中で故国にも立ち寄ったが、商人の言葉通り、荒廃の気配があった。
記憶にあるよりも街は薄汚れ、粗末な身なりのものも目立つ。
聞けば重税が課されているらしい。
一刻も早く故国を開放せねばならないと決意を新たにして、先を急ぐ。]
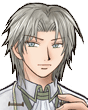
南極石の王子 クレステッド
― 『神魔の領域』 外周の森 ―
[伝承に語られる森は緑深く、静謐な気配を湛えていた。
神妙な面持ちで足を踏み入れ、最奥にあるという神魔の居処を目指す。
森の入り口が見えなくなったころ、目の前を光がちらついた。
何かが落ちてくる気配がして、両手で受け止める。
手のひらに転がったのは、白と水色の軽い結晶体。
尖った葉が見事なロゼット状に開いたその形は、見覚えがある。
土には根付かず、木や岩の上で花を咲かせる根無し草。
鮮やかに紅葉し、濃紫の花を咲かせていたが、どこか頼りなくも思えたものだ。]
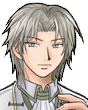
南極石の王子 クレステッド
[冷たい結晶の花を手にしたと同時に、声>>0:6が聞こえる。
この声の主こそが神魔なのだろうか。
詰めていた息をそっと吐き出し、もう一度花を眺める。
氷のように透明な結晶と、揺らめく水面のような白と水色の石。
手を上げて、身につけている腕輪を見る。
そこに嵌まるのは、やはり氷のように透明な石だ。
己の手にあるときのみ冷気を湛える天命の石。
かつてはただ護符のようにして首元に下げていたものだが。]

南極石の王子 クレステッド
[この花の石が、己の石と同じものならば。
もう一つの石は、やはり。
鼓動がひとつ、高鳴る。
あの日、父王の隣にいた「王子の影武者」の消息は知らない。
知りようも無ければ、希望を持つのも難しかった。
だが、もしも生きているのなら―――]
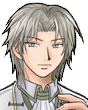
南極石の王子 クレステッド
[胸を押さえ、気を静めながら歩みを再開する。
なにはともあれ、探さねばならない。
強いて思考を止め、森の気配に意識を向けて探索を続けた。*]

南極石の王子 クレステッド
― 『神魔の領域』 ―
[森の中を歩き続けるうちに、異質な臭いに気づいた。
血臭。それもまだ新しい。
長い年月を森で過ごすうちに覚えた感覚が、導く。
やがて、前方が明るくなる。
梢がわずかに途切れているのだ。
小さな泉が木々の間から見える。
傍に佇む馬と、人の影も。>>51]
誰か。
[近づくより先に、誰何の声を投げた。
後ろ姿の髪色が誰かを思い出させて、疼く。*]
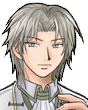
南極石の王子 クレステッド
[泉の前で人影が立ち上がる。>>142
振り向いた姿は、尚更心をざわつかせた。
確かめる口調で音が並べられる。]
それは、花の名だな。
森に入る際に授けられたものだ。
[わざわざそれを口にしたということは、彼こそが相まみえるべき相手なのだろう。
木々の途切れた場所に足を踏み入れ、全身をさらして近づいていく。
だが、相手の手が剣に伸びたのを見て立ち止まった。]

南極石の王子 クレステッド
待て。
戦う気は無い。
[声は、相まみえよと告げただけだ。
戦う理由はない。
それになにより、彼には知己の面影があった。]
そなた、
ヴィンセントではないか?
[確信をもって問いかける。
幼少期の多感な時期を共に遊び、共に学んだ相手だ。
見間違うはずもない。
『神魔の領域』に着くまでは、と与えられた加護が既に解けていることを願う。
この姿を見れば相手も気づくはずだと疑いもしなかった。**]
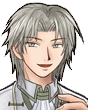
南極石の王子 クレステッド
[名を呼べば、彼の眼差しが驚きに揺らいだ。>>170
ああ。やはり彼なのだ。]
やはりそなたなのだな、ヴィニー。
私だ。クレステッドだ。わかるだろう?
[喜びに声震わせるが、相手の反応は堅い。
10年も経っているのだ。
信じられないのも無理はないと思い直す。]
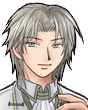
南極石の王子 クレステッド
覚えているだろう?
7歳のころ楡の木に登って、二人で落ちただろう。
そのときの傷だ。ほら。
[前髪を掻き上げて額を見せる。
生え際にうっすらと赤く残るのはそのときの傷跡だ。
乳兄弟がかばってくれなければ、大怪我をしていたかもしれない。]
10年もそなたを探さずにいて、すまなかったと思う。
苦労も掛けただろう。
詫びる言葉も無いが、今はただそなたとの再会が嬉しい。
[素直な心情を言葉に載せるが、返された視線に熱は感じられない。]
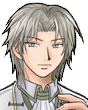
【赤】 南極石の王子 クレステッド
[代わりに、チリつく気配が伝わってきた。
殺気とも違う、ただ危険の予感だ。]
待てと言っている。
私を忘れたわけではないのだろう?
[気づけば溢れた水が足先まで来ている。
一、二歩下がり、そっと得物に手を置いた。*]

【赤】 南極石の王子 クレステッド
[忘れたわけではないと語る彼の所作は硬く、口調は敬意と共に隔意を感じさせる。
その事実に憤慨した。
彼は、私の隣にあるべきだ。
これまでの経緯など知らぬ。
こうして再び生きて出会えたからには、私の元に戻るべきだ。
それがあるべき姿だろう?]

【赤】 南極石の王子 クレステッド
よろしい。
ならばこれぞ試練と心得よう。
私は私の行く道にそなたを求める。
[宣言して、腰から二本の得物を抜く。]

【赤】 南極石の王子 クレステッド
[構えたそれは、遠目には赤銅色の細剣とも見えよう。
実際にはそれは、竹に似せて形作られた銅の硬鞭だ。
柔らかな革の鞘から抜いたそれを自然に下げて持ち、波打つ水から一度、さらに
下がる。]
――― 散!
[短い言葉に応じて、両手首の腕輪に嵌まる天命石が溶けた。
液体と化した石は手を伝って流れ落ち、双鞭に至る。]
結!
[再び言葉によって形を取り戻した石は、鞭の根元に固着して強烈な冷気を発した。
それを受けて二本の鞭はたちまち白く霜に覆われる。]
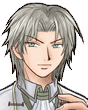
【赤】 南極石の王子 クレステッド
[握れば肌が張り付くほどの冷気を帯びた双鞭を手に、まっすぐに駆けた。
術に操られて伸びる水の触手に鞭を打ち付けて振り払うを試みながら、水の領域へと吶喊する。
殴って目を覚まさせろ、とは何の物語にあった言葉だろう。
ともかく、ただひとりの"兄弟"だけを見据えて、前へと体を運んだ。]
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新



 フィルタ
フィルタ
生存者 (4)
犠牲者 (4)
処刑者 (4)
 ★
★


