469 グラムワーグ・サーガ3 〜反撃の嚆矢〜
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新
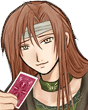
流離の勝負師 ディーク
[双子はレオヴィルへ向うという。
今、魔物に占拠されていないのはレオヴィルだけだ。
普通の子供ならば、当たり前の判断だった。
そして、ユーリエ姫の件で、彼らは追われたりはしていないのだろう。
姫の死と無関係ゆえに、とディークは判断する。
子供の姿をしている彼らに、ディークは甘かった。]
以前とは情勢が違う、気をつけてゆけ。
[行く先は同じでも、今回、双子を連れてゆくわけにはいかなかった。
レオヴィル領内にいるだけで、ディークはいつ捕まってもおかしくないのである。]
飴でもあればやるんだが、あいにくと手持ちがなくてな。
おっと、俺とここで会ったことは内密にしといてくれ。
[努めて明るく別れようと試みた。]
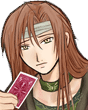
流離の勝負師 ディーク
[双子は去りがてに、それぞれ飴をくれた。>>102]
ありがとうな。
[またね、と再会を望むような声には、苦い気持ちを噛み締める。
姫と双子と自分と、和気あいあいと旅した頃にはもう戻れない。]
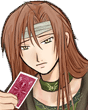
流離の勝負師 ディーク
[小犬のようにまとわりついて甘える双子を、ユーリエは可愛がった。
ロー・シェンが語るローグの旅路に心弾ませて夢見たように、双子の話も楽しく聞いていた。
盛ってるだろうとわかる話でも、彼らの巧みな話術にかかると信じてみたくなるから不思議だ。
夜に花を咲かせる石があるんだと双子にそそのかされて夜通し探し回り、身体を冷やした姫が寝込んだこともあったが、姫は叱ろうとするディークを宥めた。信じて探している間、楽しかったもの、と。
また、先方からしょげた風情で謝られれば、反省はしているのだと思った。]
──…話半分、か。
[出陣してから川の水以外、何も口にしていなかったので、さっそくもらった飴を口に放り込む。
包みの色は、2(2x1)だった。 1.赤 2.青 >>102]

流離の勝負師 ディーク
[ダダ甘砂糖味に、余計に喉が渇く。]
半分でもヤバかった…
[つくづく彼らとの付き合いを再考させられつつ、青い飴をしまいこんで、傭兵たちの後を追う。]
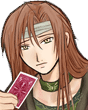
流離の勝負師 ディーク
― 回想 ―
[今から1年ほど前、ユーリエは自分の意志でレオヴィルに戻ると決めた。
「今のわたしを記憶に留めておいてほしいから、あなたとはここで別れましょう」と彼女は言った。
ユーリエの身体を蝕む病は、確実に進行していた。
むしろ、こんなに長く旅を続けていられたのが奇跡だ。
「夢を諦めていたら、わたくしはもっと早くに歩けなくなっていたに違いないわ。
命をかけて惜しくない夢なら、力を貸すと言ってくれたあなたのおかげ」
その夢を共に見るのも、この日が最後で──
旅を始めたときから覚悟していたことだというのに、傍らに気心知れた相手がいないというのは、けっこう寂しいものだと身にしみた。]
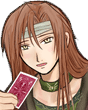
流離の勝負師 ディーク
[人生の終わりに家族を安堵させて残された時間を心安らかに過ごすべく王宮へ向った姫と、仲良し双子を送り出してしばらくたった頃、シラーの宿でひとり酒を傾けていたところへ警吏が踏み込んできて、ユーリエの死を知っているかと訊ねた。]
…多分、あんたたちより先にわかってたよ。
わざわざ俺を捜し出して知らせに来なくてもよかったのに。
[感傷的に答えたら、相手は「では認めるのだな」と色めき立ち、あれよあれよという間に乱闘になった。]
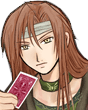
流離の勝負師 ディーク
[自分ひとり逃げ切るつもりならできなくもなかったが、「殿下」と呼ばれる男まで登場するに当たって、これは相当、込み入った話らしいと抵抗をやめておく。
未決牢に放り込まれて知ったのは、ユーリエが王宮に帰りつく前に殺されたことと、その場に残されていた凶器の短剣がディークのものであったということだった。
その短剣は、レオヴィルの軍学校を卒業する際に成績優秀者に与えられたものだ。
見栄えも使い勝手も良かったが、双子が玩具にしたがって危なかったので、旅の途中で売り払った。
それが、どうして。
警吏らが納得しなかったように、ディーク自身にも謎は解けていない。]

流離の勝負師 ディーク
― レオヴィル王国軍陣地 ―
[双子の出現で、いやがおうにも思い出してしまったが、この先は、作戦に集中すべきだろう。
川岸で、息はあるが意識のない王国兵を見つけて肩に担ぎ上げた。
負傷者を連れて戻ったという偽装だ。
そうして、防衛成功の勝利に沸く王国軍の領域に紛れ込む。
こんな作戦ができるのも人間ならではだ。オーガでは一発でバレる。]
ボーナス要求してもいいな、これ。
雇い主に、町のひとつもくれと言ってみようか。
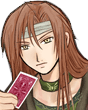
流離の勝負師 ディーク
[野戦病院に兵を届けたついでに、戦場で回収した遺品の入った袋を、そうと告げて看護兵に渡しておく。
多忙な看護兵は、今、細かいことを気にしている暇もあるまいと計算した上でだ。
後で家族の手に届けばいいものだ。死者は急がない。]
足りない品をとってきてやる。メモをくれ。
[資材置き場に入り込むために、そんな手を打つ。
そうして、そろそろ夕闇の濃くなってきた陣地を奥へと進んだ。*]
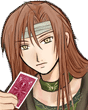
流離の勝負師 ディーク
[王国軍の中を早足で、だが怪しまれない程度には毅然と歩いてゆく。
と、盗賊一味のひとりに遭遇した。>>138
蝋燭を使った時限着火装置の自慢と、ディークが手元に置いていた子供を目撃した旨を伝えられる。]
ああ、情報感謝する。
人生、悔いなく男らしくいこうぜ、兄弟。
[マーティンの口癖を挨拶代わりにして、拳を軽く合わせ、食糧調達に向うらしい彼を見送った。
傭兵たちの刹那的で快楽的な生き方を見ていると、自由だなと思う。
あの屈託のなさ、己と何かが決定的に違う。]
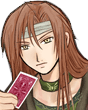
流離の勝負師 ディーク
[考えながらも、歩みを止めることはしない。
その視界の端に、身を翻す小柄な影を捉えた。>>139]
──…、
[かすかに洩れた声と身のこなしから、魔軍の拠点に置いてきた子のひとりだと察した。
どうすれば王国軍と接触できるかは、使者に出す子供を引き合いにして聞かせてきたとはいえ、魔物たちの目が前線に向いている間に脱出を計るとは、なおかつ、子供らだけで成功しおおせたとは、なかなかいい判断力をしている。]

流離の勝負師 ディーク
[ディークは、即座に子供を追い、その襟首を掴んで物陰に連れ込んだ。]
おまえひとりで脱出したのか、それとも、全員か。
[後者だと聞くと、ディークは、よし、と頷いた。
魔軍に戻らねばならない柵がひとつ消えたと、漠然と感じながら、子供の頭を撫でる。]
良くやった。
いい意味で裏切られて、俺は嬉しい。
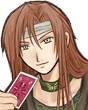
流離の勝負師 ディーク
この先も、勇気をもって切り抜けろ。
おまえたちには、生き延びてもらいたいんだ。
[短く告げて、子供を放す。
そうして自分は、篝火から燃えている薪を引き抜き、手当たり次第に天幕や荷駄に放り投げた。
どのような形であれ、潜入を発見されてしまった以上、時限発火装置の稼働を気長に待ってはいられなかった。
疾きこと風の如く、侵略するとこ火の如くあれ。
随所で騒ぎを起こして、そのまま撤退の構えだ。*]

流離の勝負師 ディーク
[声変わり前の甲高い声があがったかと思うと、子供らが手に桶を携えて消火にかかる。>>163
それを見届けることはしなかったが、どうやら作戦が失敗したらしいことは膚で感じた。
呼応して上がる火の手もなくば、動揺の気配もない。
届いたのは──]
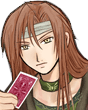
流離の勝負師 ディーク
[己の名を呼ぶ、知らぬではない声。>>166
凛としたよく通る声は、続けて、もうひとつの名を告げた。
それが、ディークの足を止めさせた。]
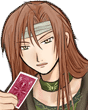
流離の勝負師 ディーク
[木の作る影の中に立って、単身追いかけてくる王国軍総大将を見やる。]
──久しいな。
[軍学校時代の悪友は、今や、世界の命運を背負う男の顔になっていた。
だが、そんな感想は口にしないまま、]
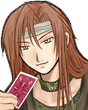
流離の勝負師 ディーク
おまえの活躍は、見させてもらった。
魔軍相手に、ずいぶんと踏みこたえているようじゃないか。
[ロー・シェンが前に出るなら一歩下がり、そうして互いの距離を保ったまま、問いに答える。]
どうするも、 レオヴィルに俺の居場所があるとでも?
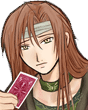
流離の勝負師 ディーク
[マーティンが捕らわれたと聞いた時点で、ディークを魔軍に繋ぎ止める最後の柵もなくなっている。
だが、この地がディークにとって危険であることは変わらない。
その焦燥を知ってか知らずか、目の前の男は微笑む。>>193
会えて嬉しいと。
荒くれ者の世界では、それは相手を殴ろうとする者の台詞だが、ロー・シェンの場合は言葉どおりの意味だとわかっていた。]

流離の勝負師 ディーク
[「俺を、助けて欲しいと、そう言おうと思ってた」と剣の柄に手をかけたままで言ってのけた男は、その申し出を後回しにして、胸に手を当てて一礼する。
その唇から出たのは、丁重な礼の言葉だった。>>199]
…、 ハ!
今のはよかったな。 不意を打たれたぞ。
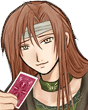
流離の勝負師 ディーク
[ぎこちなく笑う。
ロー・シェンの代わりにユーリエに世界を見せてやろう、というのは誰にも打ち明けたことのない理由だったものを。この男には気づかれていたと知って、どこか切ないほどだ。
理解されることの、渇望。
まして、ユーリエの面影を宿すその表情に揺さぶられる。
もう、後ろに下がるのは止めていた。]

流離の勝負師 ディーク
[それでも、努めて冷徹な視線でロー・シェンを見返す。]
さて…と、旧交を温めたところで、現実に戻ろうか。
殺した魔物も、殺された兵も、屍鬼になって戻って来る状況で戦い続けても、残るのは焦土だけだ。
おまえも王都アルテスをクレーターにしたくはなかろう。
おまえの首をとって帰れば、褒美に町のひとつくらいもらえる。
そこで、生き残りの人間でも集めて暮らすというのはどうかな。
おまえも無駄死ににはならない。
── そのために、死んでくれるか?
[それ以上のことができるのなら聞かせてみろと、言葉にはせず、求める。*]
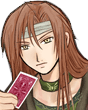
流離の勝負師 ディーク
[ロー・シェンの主張を聞き、そこに狂信も悲壮感の欠片もないのを見て取った。]
地に足のついた男だ。
[そして、命をかけても惜しくない
そういう人間の光と熱は──ディークを惹きつけた。]
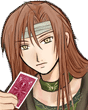
流離の勝負師 ディーク
[ロー・シェンが剣を抜くのを見て、ディークは肩を竦める。
魔法のカードは装備しているが、剣の類は帯びていない。]
…面倒くさいな。
そういうのは、マーティン親分さんとやってくれ。
[口とは裏腹、策を繰り出すときの目で告げる。]
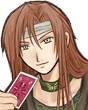
流離の勝負師 ディーク
皆の前で、親分さんに勝ってみせろ。
あの人はわかりやすい。
おまえの力を認めれば、喜んでおまえに従う。
そうすれば、俺も荒くれ共もまとめておまえのものだ。
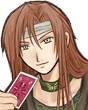
流離の勝負師 ディーク
[学生時代に戻ったような口調で、ロー・シェンは提案を受け入れた。
皇太子になっても変わらぬその自由さを、ディークは愛した。
背を晒して平然と歩くロー・シェンの後についてゆく。]
背負う男になったな。
[以前から、抜きん出たものを持っていた男ではあるけれど。]
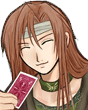
流離の勝負師 ディーク
[ロー・シェンはマーティンの縄を解かせ、皆の前での勝負を挑んだ。]
ハゲって…、 火に油そそぐなような真似を。
[これは果たし合いではなく喧嘩だと、その一言で宣言してのけたようなもので、苦笑のうちにも感嘆する。
素手どおしでの闘いになると判断したロー・シェンは即座に皇太子の剣を放り投げ、ディークは一歩も動かず手を伸ばして受け取った。示し合わせたわけではないが呼吸はぴったりだ。]
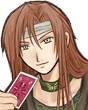
流離の勝負師 ディーク
[直後に肉体と肉体がぶつかり合い、皆は、わっと響めきたった。
学生時代も、ロー・シェンの周りにはいつも人が集まって楽しそうにしていた。
彼には、人を惹きつけるものがある。
それこそが──英雄たる資質。
ディークは預かった剣を肩に乗せて保持し、闘いを見守る態で、周囲をとりまく人々を観察した。
試合の行方を案じはしない。
ロー・シェンが負けるはずはないと、確信して言える。]
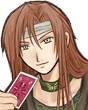
流離の勝負師 ディーク
[ロー・シェンの闘いは舞いのように力強さの中にも美しく、荒くれ者たちすら身を乗り出して惹きこまれてゆく。
猛禽のような蹴りが決まると、どっと歓声があがった。
ロー・シェンがマーティンの強さを讃えて、その身を引き起こす。
決着はついていた。 目に見える形でも、心の中でも。]

流離の勝負師 ディーク
[だが、不意にロー・シェンは戦人の顔になって踵を返す。
敵が動いた、と。
ディークは、マーティンの傍らに身を屈めて、短く告げた。]
親分さん、こいつを預かっているんで、ちょっと行ってくる。
[皇太子の剣を見て、マーティンは、「遅れんな」と顎をしゃくった。
ディークは感謝の色を返し、ロー・シェンを追った。*]
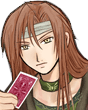
流離の勝負師 ディーク
[早足に通り抜けながらも、使えるものを頭に入れてゆく。
と、ロー・シェンは今ひとりの将官と合流した。
モンテリーの王弟。親しいはずもないが、存じ上げてはいる。
再会の間隔からすれば、ロー・シェンとよりもっと近くすらあるのだ。
彼が浮かべた表情を見て、把握されたと察した。
避ける色はみせず、会釈だけしておく。]
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新



