381 四君子繚乱
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新
柊の氷華 ジークムントは、聖蓮の花神 マレンマ を投票先に選びました。

柊の氷華 ジークムント
私も同意見だな。
[蓮魔の言い捨てる言葉>>2に短く返し。
蓮鈴の音>>3聞きつつ、眼差しはその従華の方へ]
[己が僕と言葉は交わさぬ。
ただ当然のように、互いの対戦者向け一歩を踏み出す]
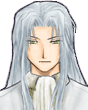
柊の氷華 ジークムント
― 戦舞台 対岸 ―
[対戦者が走る一方、特に急ぐでもなく、悠々と歩を進め。
会話が可能な距離に追い付いた所で、足を止める]
名前?
――『氷華』、今代を指して言うなら『柊の氷華』だが。
[二つ名を答えるは、相手>>8の要望とは違ったかもしれぬが]
何故そのようなことを訊ねる?
[隷属者の名すら聞かず仕舞いの氷華は、訝しむ口調で訊き返す。
掌を上向けたその右手には気が凝結し、いつしか氷の細剣が現れていた*]
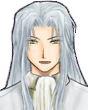
柊の氷華 ジークムント
ふん、そうか。
[聖蓮の従華が口にする名前>>12。
蓮魔はともかく、己の従華のそれは初めて耳にした。
かと言って特に感慨もない声で答える]
[何故彼が彼自身の名を言いよどんだのか、それはわからなかったが]
それは有難いお言葉だ。
だが生憎と、私は人を使う予定はないのでね。
[忠告も平然と受け流す。
そこに響く気合いの声と、そして何かの機構が動く音>>13]
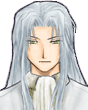
【赤】 柊の氷華 ジークムント
― 戦舞台・対岸 ―
[対する従華が名乗るのは、先に言いよどんだのとは全く異なる響きの名>>*0]
そうか。覚えてやろう。
呼ぶ時は永遠に来ないがな。
[背の半ばまでを覆う、長い銀の髪。
それを掠める如き軌道で、水の針が飛ぶ。
対して氷華は、緩やかな軌道で右手上げ、針の周囲へ冷気生み出す。
直接撃ち落とすではなく、水を氷へ変じで、自らの力で操るために]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
この程度では抜けぬよ。
[氷と化した水針は、急激に速度を減じ地に落ちた。
威嚇程度の意味合いであろうが、わざわざ受けてやる義理はない]
さて、これだけ離れれば、少し広き空間に力を及ぼしても良かろう。
[言って、垂直に立てていた細剣を、外側向け鋭く振るう。
忽ちの内に、氷華とハルトを包むのは氷点下の冷気。
人の身であれば呼吸すらもままならぬ気温であった]
そなたは、この程度で枯れる花ではなかろうな?**
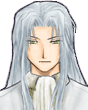
【赤】 柊の氷華 ジークムント
[ハルトの得物の機構が動き、音が響く。
その間にも、こちらの起こした冷気は少年の身を包んだ。
生身の少女ほどではなかろうが、それでも震えるほどの寒さは感じるらしい>>*6]
威勢のいいことだ。
[得物を構えるハルト>>*8へ半眼向ける。
『譲葉』では見たことのない武器、その身は燃えるような赤。
ハルトが引き金を引けば、爆ぜるような大音が響く]
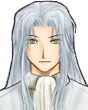
【赤】 柊の氷華 ジークムント
[寒気を突き破る弾丸が、渦巻く蒸気を巻き起こすのを、観察するだけの猶予はない。
細剣の切っ先を地に向ければ、落ちた霜が一瞬にして集い、分厚い氷の壁となる]
[しかし――夏の陽射しの熱持つ弾丸は、その壁の中心を一瞬にして溶かし、抜いた]
――ほう。
[蒸気により残された軌道と、壁に接した際の僅かな減速。
それは氷華が銃弾から身を逸らすことを可能とし、蓮の実は白の外套の腕辺りを掠めて落ちた]
蓮は蓮でも、紅蓮という訳か。
[損害はない、しかしその一撃は、術を主体に戦う四君子を確かに『動かした』のだ]
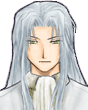
【赤】 柊の氷華 ジークムント
一発だけかね?
[見慣れぬ得物に、魔弾と等しき蓮の弾丸。
なれどまだ、氷華を溶かすには足りぬ、と]
ならばこちらは、こうだ。
[細剣の切っ先を上へ向ければ、壁は穿たれた部分を中心に砕け、無数の大きさの疎らな氷の楔へと変化した。
それらは細剣の指揮に合わせ、鋭き先端をハルトへ向ける]
穿て。
[その言葉を合図に、楔はハルトの身に向けて殺到した*]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[魔法使い、と評する言葉>>*15に肯定も否定も返さず。
楔がハルトを追い詰めていくのを、ただ色のない瞳で眺める。
しかしハルトは身を翻し、転がり、楔の直撃を受けることなくかわしていく>>*16]
はっ。
[低姿勢で駆けるハルトの手元から、再び響く破裂音>>*17。
今度は一枚壁ではなく氷塊が、弾丸の軌道へ次々落下し、砕けることにより勢いを殺す。
足を狙う一発は、外套の端に僅かな焼け焦げを残し通り過ぎた。
しかし防御へ意識向けた故に、楔の動きが緩慢となったことに、相手は気付いただろうか]
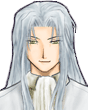
【赤】 柊の氷華 ジークムント
――ふん。
[紺野、と護花の名らしきものをハルトが呼ぶ。
氷神は一瞬眉を顰めるも、口調は変えぬまま]
協力? たかだか二度、己の代理に戦わせるだけの存在であろう?
元が身勝手なのだから、納得も何もなかろうよ。
[主張を吐き出しながらも、ハルトは徐々にこちらとの距離を縮めつつあった。
術主体のこちら相手に、接近戦を狙っているのは読めた。
かといって身を翻し距離を離すは、氷華の足では得策ではない]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
――凍柊結界。
[短く唱え、呼び出すは防御の術。
氷華の周囲で、霜含む冷気が緩やかに渦を巻き、更に温度を下げた。
やがて渦の中には、柊の葉を模した薄き氷の刃が、生い茂る葉の密度で現れる。
物理的に侵入を阻みはしないが、突入すればそれなりと痛みと寒気を与えることだろう*]
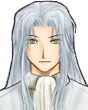
【赤】 柊の氷華 ジークムント
頭下げて?
[ハルトのその言葉>>*25に、氷華は心底不思議そうな顔をした]
――ふん、ならば蓮魔は、そうしたとでも言うのかね。
[バカだなんだと言ってはいるが、一応の信頼関係はあるらしい蓮の主従。
迫りつつあるハルト向け、投げ掛けるのは純粋な問い]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[結界の出現により、周囲の気温は更に下がる。
――否、氷華の周囲へ集中した分、離れた場の気温はやや上がってはいるのだが、接近している今そうと気付くのは難しいであろう]
[柊、触れればひいらぐ葉、人を寄せ付けぬ冷気。
確かにそれは、氷華の一面を表していた>>*26]
無謀であるな。
[凍れる柊の茂みの内から、氷を割って跳躍するハルト>>*27を見やる。
ただ跳躍するだけで超えられる結界を超越者たる氷華が張るはずもない]
[だが、柊の群れへ向け、落下するかに見えた少年は。
紅の銃で持って、足元の氷を打ち砕く。
そこに開いた蓮の花は、一瞬で凍り砕け散りつつも、ハルトの身を受け止めた>>*28]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
――よく跳び込んだ。
[冬の領域の内側、蓮魔と護花にも視認出来ぬ空間に一人と一柱。
足に刻まれた赤を見やりつつ、ぽつと零した言葉は、ハルトの耳にのみは届いたかもしれぬ。
表情変えぬままの抑揚乏しき声、意味を正しくは捉えられなかったかもしれないが]
さて、手の届く距離まで来たが。どうする?
[水の護りを得た所で、少年の動きは止まったようにも見えた。
氷華にとって結界は無害、そして躊躇う理由もない。
鋭き細剣持つ右手を前に、少年へ切っ先突き付け半身の構えを取る]
[接近戦は不得手、なれどこの状況ならば一番効果的とばかりに、少年の肩向け細剣で突きを放った*]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[氷と水の相転移。
氷華は水を転じた氷すらも己が力として操るが、逆に水や熱を自在に操る者なら、氷の力を削ぐことは出来よう。
水を受け鈍った柊の刃、であるが今は結界の保持ではなく剣による一撃へ意識を向けている氷華は、細やかなその変化>>*35をまだ気に留めてはいなかった]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
剣の形をとっているのだ、使うべき時には使うものだ。
[ハルトは細剣の一撃を、驚きの声と共に受け止めた>>*36。
刃は銃身にて防がれるが、その時舞い落ちたのは紅蓮の花弁。
極寒にも萎れぬ力持つそれは、炎へ変じ燃え尽きる]
――ほう?
[花弁の出所は銃身、そしてその赤には剥げ落ちたような傷がある]
成程、鍍金であったのか。
[正確には塗装であろうが、見栄えのみの力を揶揄するように言い放つ]
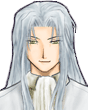
【赤】 柊の氷華 ジークムント
[放たれた鋭い水刃。
外気そのもので凍り付かせつつ、細剣の柄で打って軌道を逸らす。
完全回避とはいかず、外套の脇腹に裂け目が出来るが、この距離では防御術を呼び出すは間に合わぬと判断してのこと]
そうであったか。
[言葉を交わした回数は多くはないが、確かに頭を下げる様子など想像も付かぬ]
そなたも面倒なことをするな。
長く付き合う相手でもあるまいに。
[代理戦争が終われば離れる程度の相手と、当然のように断じつつそう口にする。
眼差しはハルトの銃を持たぬ方の手、どうやら水刃を作り出そうと苦心しているらしい]
未だ水に拘るのかね?
[無意味と一蹴するように、細剣振るいその手を弾こうとする*]
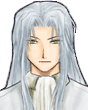
【赤】 柊の氷華 ジークムント
[細剣を受けたハルトは、水刃のナイフを手放す>>*47。
どうやら彼の方も無駄だと感じ、思考を切り替えたらしい]
――ふん。
[こちらへの頷きと共に、語られる言葉>>*48。
氷華は耳を傾けているかの如く、しばし動きを止める。
――実際は、じわり、じわりと結界内の温度を下げていた。
逆に結界外の冷気は収束し、少し離れれば肌寒い程度に戻っているが、内部からそれと気付くのは難しいだろう]
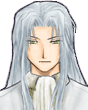
【赤】 柊の氷華 ジークムント
異界の神に、それを説くのかね?
ただの人でしかない、世の理も違う世界に住むそなたが。
[正しい正しくないだの、良い王様の在り方だの。
どうやら異界の尺度で量って、主君に説教しているらしい]
それで、変わると思うのか?
[問いにあえて、主語は付けない]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[構える姿勢は低く、眼差しには覚悟が見て取れる>>*49。
そして駆け出す、その身に氷の柊が触れるが、思うほどの負傷を与えてはいない。
掛けられた水により氷が歪に変化していると、はっきり認識したのはその時のこと]
誰が似た神と――!
[口調をやや荒げたのは、発言への怒りと、回り込む動きへ対応が遅れたことによる焦り。
温度下げた空気の内より、無数の礫が生まれハルトの進路上に配置されるが、痛みを覚悟した彼を止め切れはしないだろう]
小癪な!
[触れそうな近距離で、紅蓮の銃口が向けられる。
悠々たることも忘れたように、咄嗟に生み出され多重に並べられる氷の盾。
しかし紅蓮の熱を得た弾は、勢い削がれつつもそれらを貫通する]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
――届かされた、か。
[ぽたり、脇腹より液体が滴る。
血のように滴り落ちるその色は蒼。
程無く氷が傷を固め、重傷には至らぬが、明確な負傷をしたことには変わりがない]
[しかし、ハルトの方も更なる寒気と礫にその身をさらされていたはずである。
その時の状態は果たして如何なるものであったか*]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[こちらも手傷を負ったが、ハルトもまた負傷し、冷気によりあからさまに体力を奪われてもいた>>*59。
千年の冬を齎した神の力を継ぎし者、如何なる術よりも純粋なる冷気こそが、最大の武器となろうか]
[寒さのせいか朦朧となりつつも、ハルトはまだ言葉を返す>>*60。
まとまりのなくなりつつある言葉で、それでも訴え続けようとしていた]
――ふん。とんだ望みであるな。
神と言っても所詮は異界の存在。
その記憶に残ることに、何の価値がある。
[従華の任を解かれれば加護を受けられるでもなく、覚えめでたいことになんの利点がある訳でもない。
情緒を解さず、実利のことしか考えぬ氷神には理解出来ぬこと]
[だが、紺野――護花の名が出された時。
ふと隷属させる前の、気丈に立ち向かう少女の顔が思い出された]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
強がりもそこまでにしておくがよい。
[体のあちこちを赤く染め、逆に肌色は青白い。
そのような状態でなお、ハルトは真正面からこちらへ銃口向ける>>*62]
――終わらせるには良い頃合いか。
[氷華は二人の周囲を包む結界を解いた。
歪な柊はバラバラと地に落ち、余剰の冷気は望み通りハルトの身に纏わりつく。
その風の動きを追うように、落ちた柊葉もまた集い、成長する巨大な結晶となって、ハルトの足を地へ縛るべく伸びる]
[そして彼の頭上には無数の氷柱が、城の装飾照明にも似て、切っ先を真下に向けつつ整然と出現し始めていた**]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[ハルトは急いての一撃はせず、待ちの姿勢。
凍れる音のみが響く、短い静止。
その時、氷華の意識は舞台の対岸に、高まる花神の力を感じた>>*67]

柊の氷華 ジークムント
心凍てつかせ舞い続けよ。
[水刃が殺到する一瞬前、結界より一陣の冷風が走り、護花の身に纏わりついた。
それは寒気を操る力か、それとも純粋な身体能力か、護花の望む力を高め、蓮魔の攻撃を捌く一助となるだろう]
凍れる冬にて時を止めよ、我が僕。
[それきり言葉を掛けるでもない。
ただ勝利のみを要求する]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[再び視線をハルト>>*68へ戻す。
凍てつく風に身を凍らされ、勝敗が決するは目前と見えていた。
しかし、その銃と構える腕はまだ凍り付いてはおらず。
その眼差しには、勝負を諦めぬ意志が宿っていた>>*69]
――そなたの主が、真に王華に相応しいと思っているのなら。
[ざ、と氷華はハルト向け、正面から一歩を踏み出す]
その魔弾にて私を穿ってみせよ!
[周囲に吹雪渦巻かせ、氷華は細剣握る右手を合図の如く振り上げる。
頭上で豪奢な装飾の如く成長した氷柱の束は、ハルトへ向け一斉に落下する*]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[蓮の花弁が舞う、そこから生じるのは夏の陽射しを思わせる熱>>*73]
相棒だから?
[問い掛けに返る答えを受け、ぽつりと呟き瞑目する]
――そうか。
[再び目を開けば、咲き誇る紅蓮の花が眼に映る>>*74]
やはり、冬には――
[その先の言葉は、空気を切り裂き落ちる氷柱の音に阻まれて、誰にも届かない]

【赤】 柊の氷華 ジークムント
[氷華の周囲に、ひらひらと柊葉が舞う。
相手を傷付けるためでなく、その冷気にて術者の身を守るために。
しかしそれらは、抗うような陽射しの熱量受け、次々に解けては消えていく]
まこと、……暑苦しき力よ。
[轟音と共に開く紅蓮の華>>*75。
水が再び氷となり氷神の支配下に置かれる速度を、その熱はついに凌駕しつつあった。
爆発的な水蒸気が視界全てを白く染め、彼我の姿は見えなくなる。
強烈な上昇気流が、白い外套を激しくはためかせ――*]

柊の氷華 ジークムント
[ハルトの渾身の一撃は、氷華に届いたか否か。
仮に届いたとしても、まだそれとは認識出来ぬ刹那。
晴れつつある水蒸気の向こうに、色取り取りの蓮花>>74を見る。
雪覆う白き冬に、似つかわしくない夏花の彩]
…………ふ、
[笑みに似た響きで息を吐く氷華は、かつて足を踏み入れた先代の領域を思い出していた。
先代の象徴花は雪割草、当代の象徴花は柊]
[その二者の共通点は、雪中に在りて常緑*]
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新



 フィルタ
フィルタ
生存者 (3)
犠牲者 (4)
 ★
★ ★
★ ★
★処刑者 (4)
 ★
★ ★
★ ★
★
