381 四君子繚乱
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新
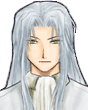
【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
[少女が意識落とす間際。
白さのない呼気を吐く、その刻を見計らったように。
氷華は少女の唇を、己が唇でもって塞いだ。
右手は顎に手を掛けて上向かせ、左腕を脇下から背へ回して]
[氷華の顔に相変わらず色はない。
淡々と、まさに儀式の手順をこなすが如く。
そして僅かにこじ開けた唇の隙間からは、氷の結晶が一欠、少女の口中へ押し込まれる。
反射的に呑み込んでしまう程度の勢いで]

【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
[それは、少女の身を内より凍り付かす、隷属の呪を込めた結晶。
やがてそれは心臓に達し、心すら凍らせる楔となって打ち込まれる**]

【秘】 柊の護花 コンスタンツェ > 柊の氷華 ジークムント
[重い体は氷れる神の為すが侭。
抱き寄せられる其れは、抱擁ではなく体勢を良くする為が目的。
青褪めた唇に、尚冷たき透徹した氷の如き唇が重なる。
意識がはっきりとしていれば、初めての口接けだったのにと思う事もあったろうが]
――…、…、……!
[微かに開いた唇から、氷の結晶がするりと這入り込む。
呑み込める程、小粒程らしき結晶は、自らの意志あるが如く触れた箇所、その周囲問わず、内側から蒼醒めさせ霜付かせる、]
…ゃ…… だ
[内側から凍り付かせる呪は、痛みか、其れとも神経が反射を行わせているのか、リリの躰はびくり、びくりと跳ねる。]
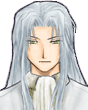
【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
[異界の少女が思う唇を重ねることの意味、とりわけ初回が特別であるということなど、氷華が知るはずもない。
人と触れ合うことを厭う氷華にとっても、その行為は初めてのことではあったのだが]
まだ少し温かったな。
[氷の欠片を舌で送り、唇を離してからの第一声がそれ]
身が完全に凍るまで待つべきであったか――とはいえ、命を落とされでもしたら敵わぬからな。
[背を支える腕は、先は欠片を呑ませるに都合のいい姿勢を取らせるため。
今は少女の変質を観察するためにあった。
右手を軽く顎に添えつつ、僅かに空いた口の奥に、霜が広がり行くのを眺める]
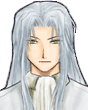
【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
――活きのいいことだ。
[凍れる内側から、冷たい息とともに微かな抵抗の声を吐きながら。
少女の躰がびくり、びくりと飛び跳ねる]
耐えよ、感覚すらも凍りついたなら、もう痛みを感じることもない。
[苦痛に喘ぐ少女を、感情の一欠片も浮かばぬ眼差しが見た。
氷神には、そもそも寒いという感覚などない。
そして痛みに対しても、血の通わぬ身であるからか、人間ほど鋭敏に感じることはなかった。
故に、それはどこか己の力が、人の身にどのような結果を齎すか観察するようでもあったか]
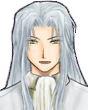
柊の氷華 ジークムント
― 凍柊の領域―
[少女が悲鳴を上げる>>215。
心臓を穿つ楔は、物理的な損傷は齎さずとも、見た目通りの激痛を与えているのだろう。
そして、それを相転移の合図としたかのように、内から喰い尽くすが如く、氷霜が少女の内側を侵食する。
それは少女を抱え外側を観察する氷華の目にも、皮膚の内側より突き出す結晶として見えていた]
――成程、こうなるのだな。
[二代目の氷華にとって、隷属の儀を行うは此度が初。
それが少女の身へ齎したものを、苦しむ様など意に介さぬように、ただ眺め呟く*]

【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
だが、これでは些か不格好に過ぎるか。
[氷華は顎に添えていた右手を離し、少女の鳩尾――心臓の位置する辺りに当てた。
鳩尾の中心を、強く押さえるような動作をすると同時、心臓や皮膚の内側より突き出した結晶が、呼応するかのように内へと一斉に押し込まれた。
そして、今度はゆっくりと――少女の身を、従華として相応しく飾り立てるが如く、美しき結晶が伸びる。
その頃には、少女の身から体温は消え去り、氷華と等しく氷の彫像の温度となっていた]
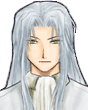
柊の氷華 ジークムント
[最後の一撃が少女の心臓に加えられ、内に生じた氷の結晶は完成する。
それは、心身の変質が完了したと同義]
――動けるか?
[気遣いではなく、確かめるような冷えた声が、少女へ呼び掛ける。
氷の如く冷え切った身は、先の一撃を最後に痛みすら感じなくなっているだろう。
にも関わらず、その身は少女の意のままに動かせる。
そのような奇妙な状態――と、思う心がまだ残されているかはわからぬが*]

【秘】 柊の護花 コンスタンツェ > 柊の氷華 ジークムント
[まだ熱ある躰も氷の結晶が呑まれ奥へ向かうにつれ、凍えきる。
熱は無く、一切の体温も無く、凍結した。
生命と言える拍動も停まりきる。
喘ぐように、唇が微かに動く。]
――……
[冬神の言う通り、痛みは無くなっていった。
凍れる事による痛みも無く、神経まで凍って、澄みきるような綺麗な感覚が広がる。
全ての感覚が消え去る直前に感じたのは、恍惚とも…苦痛から解放され、氷雪の世界を楽園と感じる安堵の様なものか。
其れは冬神が先に告げた>>111通りのものだろう。]

【秘】 柊の護花 コンスタンツェ > 柊の氷華 ジークムント
[されるが侭に、鳩尾に力を加えられれば、まるでそんな玩具のように、結晶は押し込まれ、代わりに美しい蒼く透き通る氷の結晶が伸びてゆく。
翅の様な其れは、羽撃かせて浮く事の出来る代物では無いが、冬と氷雪の精霊の様な趣をリリだった少女に与えた。]
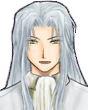
柊の氷華 ジークムント
[次にその身が意志を持って動く時、それは氷に等しい温度に変質していた。
従華として力得たことを示すように、その背からは蒼き氷の結晶が、翅の如く生えている。
それはまるで、かつての氷華との同族、氷雪の精霊を思わせる姿であった]
――よろしい。
[問い掛けに返る、従順な言葉>>219を聞き頷く。
相変わらず氷華の顔には、如何なる感情も浮かんではいなかったが]
これより契約の証を刻む。跪け。

柊の氷華 ジークムント
[己の変貌を疑うことなく、異界の仕組みすら自然に理解した少女が、その言葉に逆らうことはないだろう。
望む姿勢を取らせた後、氷華は右手に己の得物――氷の細剣を呼び出した]
――我が剣、
[す、と右手伸ばし、細剣の切っ先を鎖骨の下へ触れさせる。
鋭き先端は僅かに皮膚を破るが、血が溢れ出ることはない]
そなた本来の名と意志は捨てよ。
――これよりそなたは、『柊の護花』と名乗るがよい。
[下命と同時、切っ先を中心に少女の肌へ、四弁の小さな白い花の徴が現れる。
かつての少女>>213が暖かな思い出と共に知っていた、柊の花の形。
今、それは隷属の証として、少女の身に刻まれた**]

【秘】 柊の護花 コンスタンツェ > 柊の氷華 ジークムント
我が主、貴方様のことはどうお呼びしましょう。
[呼び方は無くとも不都合では無いが、ひとつ問いを置いた。*]
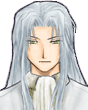
柊の氷華 ジークムント
― 凍柊の領域 ―
[隷属の徴を刻み、名を与える。
それを受ける護花>>223には、絶対的強者にも物怖じせずに反抗した、先のような意志は微塵も感じられない。
隷属が完全になされた姿を見て、氷華は僅かに眉を動かしたが、表情らしきものが表れたはそれのみであった]
[ざわ、と雪落とした傍らの柊が、常緑の葉を寒風に揺らした]

【秘】 柊の氷華 ジークムント > 柊の護花 コンスタンツェ
『氷華』、と。
名が必要ならばそう呼ぶが良い。
[従華よりの問いに答えたは、かつての主君より受け継いだ名。
二代目個人を示す名もない訳ではないのだが>>87、それを口にすることはなかった]
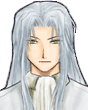
柊の氷華 ジークムント
――そろそろ、戦舞台への路が開く頃か。
[護花へ立ち上がるよう手で促し、氷華は眼差しを領域と別の空間繋ぐ場へ向ける]
戦いの術も、既にその身に刻まれたとは思うが。
[再び護花へ眼差し戻し。
氷華は僅か、思案する]
四君子相手に、先のように素手で殴り掛かる訳にもいくまい。
ひとつ、武器をその身の内より呼び出して見せよ。
[氷華の得物である細剣は、術の結晶にして媒介。
同じように氷より何かを生み出す術は、護花も身に付けているはずと。
その力と適性を確かめるも兼ねて、命ずる*]
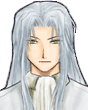
柊の氷華 ジークムント
― 凍柊の領域 ―
[千年に一度しか開かれぬ路。
力ある者でもそこに至れぬのは、世界の理や目に見えぬ結界故、だろうか。
いずれにせよ、従華として力得た少女は、その目に見えぬものを察知することも可能らしい>>235]
[そして彼女は、求めに応じその力を示す。
胸前で両手を交差し、生み出されるは鈍色の槍斧。
少女の身には余るであろうそれを、護花は片手でひとつ回転させ、危なげなくその石突を雪に置く。
つい先程まで、戦いを知らぬ少女だったとは思えぬ身のこなし]
及第点――ではあるが。
四君子へ届かすに足りるかどうか。
[問うても相手には返しようのない問い。
氷華はふむ、とひとつ声を落とし]

柊の氷華 ジークムント
[軽く身に力籠めつつ、半身となって剣を右手に構える。
常には打ち合いには使用せず、術を指揮するに用いるのみの細剣。
しかし今は、持ち主の意に応えるように、細く鋭い刃は氷を纏い、厚みと硬さを増す]
我が剣にて受ける。
戦での振る舞い、示してみよ。
[護花に向け求めるは、力確かめるための一合*]

柊の氷華 ジークムント
― 凍柊の領域 ―
[求めに応じ、得物を手にした護花の躰は宙に浮く。
白き空を滑空する様は、常人には決して為せぬ業>>244]
[地に引かれる力も借り、護花の身は矢の如く翔ける>>245。
氷華は刃を立て、刃先に左手添えて、墜落よりなお疾いその一撃を受け止める]

柊の氷華 ジークムント
――見事。
[ビシ、ビシ、と音立てて。
穂先を受け止めた刃に罅が入る。
術の媒介ゆえ強度を重視した得物ではないが、それでも同じ氷の力持つ一撃で、それに傷を付けるとは。
隷属は問題なく為されたと、評価を下す]
これならば、四君子相手の対戦でも形になろう。
――では、向かうか。
[短く告げ、返事を聞くより早く踵を返す。
向かう先は、領域と戦舞台を繋ぐ場。
氷華の力により修復され、再び細剣となった得物の切っ先を地に着けば、前方には戦舞台へ伸びる氷の橋が出現する]
[従華を後方へ従わせ、氷神は戦の場へ進む*]
― →戦舞台へ ―
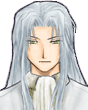
柊の氷華 ジークムント
― 戦舞台 ―
[従順なる護花>>252を後方に従え、氷華は戦舞台へ降り立つ。
眼差しは鋭く硬く、遊びを感じさせぬ表情で周囲を見回し。
真っ先に目に留まるは、蓮魔とその従華の姿]
――また、煩き者が現れたな。
[この主従がそのまま対戦者となるかはわからず。
蓮魔の過去も思いも知らぬ氷華は、表情変えぬまま言葉の届く距離まで進み出る]
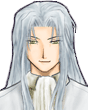
柊の氷華 ジークムント
私の初戦は、誰が相手でも構わぬが――
そなたは私を相手にせぬ方が良いだろうな。
一勝でも得たいのであれば。
[相手の持つ力は、水と花。
いずれも氷雪に対するには、不利な力であろうと*]

柊の氷華 ジークムント
― 戦舞台 ―
[氷華がその身に纏うのは、手首や足許までを覆う、動き回るには不向きと見える長い外套。
襟巻等、部分ごとに僅かな色合いの違いはあれど、全てが白。
唯一色を持つのは、左の胸元に飾られた柊の二葉のみ]
事が済めば、悠長に待つ理由もなかろう。
[繋がりを得るのではなく、ただ力を持って隷属を済ませたのみとは、素っ気ない言葉により知れようか]
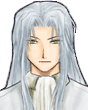
柊の氷華 ジークムント
不利な相手だから負けたなどと、言い訳されても敵わぬのでな。
[怒りもなく返される言葉と同時、響くのは蓮鈴の音>>266。
氷華は涼やかなるその音すらも、煩わしさを示すように眉を顰めた]
[蓮魔の眼差しは、一時こちらの従華の方を見る。
氷華はそれを気にすることもなく、ただ値踏みの眼差しで蓮魔とその従華を見た]
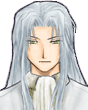
柊の氷華 ジークムント
白貴族?
[さて、その従華の第一声>>267。
貴族とは何かと訝しむが、わざわざ問うことはせず]
[しかし従華はその恐ろしさよりも、後方に控える護花が気になるようだった>>268]
紺野?
――嗚呼、護花はそういう名であったのか。
[名など気に留めぬ、とばかりに言い放つ。
蓮魔の従華は、少女の異変にも気付いた様子であったが、説明する気もなくただ一瞥を送る]

柊の氷華 ジークムント
……ほう?
[蓮魔の宣>>275に、氷華は疑問符と共に一瞥を送る。
そう決意するに至った理由を、こちらは与り知らぬ]
[笑みを消し振り抜かれた錫杖、輝く水飛沫が主従の周囲に撒かれて消える]
何故そう定めたのかは知らぬが――我らはただ一勝を収めるのみ。
[呼び出された氷の細剣が、氷華の手に握られる。
切っ先を地に着けば、氷点下の冷風が、氷華と護花の周囲に渦巻いた*]
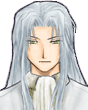
柊の氷華 ジークムント
煩いぞ。
[主の定めた対戦相手が不服なのか、喚く従華>>280へ一瞥くれる]
主の意に逆らうとは、躾がなっていないのではないか?
[口にされた無礼な評価は聞き流し、態度への非難は主へ向ける]
[しかし、やはり蓮魔の従華の興味は護花の方へあるらしい。
歩み寄り声を掛ける>>281のを目に留めるも、何も言わず好きにさせた*]

柊の氷華 ジークムント
― 戦舞台 ―
力なき花が枯れた。
それだけの話であろう?
[>>285先代の『氷華』が為した『永き冬』。
己には関係ないことと否定はせず、ただ『氷華』として、思うままの答えを返す]
考える必要などは感じぬな。
王華となる以外の意味合いを、この選に持ち込んで何になる。
[復讐だか何だかは知らぬが。
何であれ、戦いそのものに意味を持たすことなど、氷華には理解の出来ぬこと]
そなた自身に思う所あるならば、従華の手を煩わせずとも良かろう?
[しかし、奇しくもこの従華には。
既に戦う意味合いが齎されたらしかった]
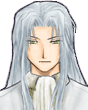
柊の氷華 ジークムント
何故だ? 性別に何か意味でもあるのか?
所詮は一刻隷属させるだけの存在、戦いを負わせる相手に気に掛けるも何もなかろう。
[苛立ちと共にぶつけられる抗議>>286。
氷華は動じず、平然と答える]
[しかし、それより何より――
護花に与えた変質が、蓮魔の従華に怒りを覚えさせたらしい>>287]
何だ、護花の有様がご不満かね。
戦に相応しく心身を変えたに過ぎないのだがな。
[それっきり無言にて、護花から離れ蓮魔の許へ戻る従華。
相手が如何なる感情を覚えようが、関係ないというように、氷華は表情変えずただ眺めた*]
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 エピローグ 終了 / 最新



 フィルタ
フィルタ
生存者 (3)
犠牲者 (4)
 ★
★ ★
★ ★
★処刑者 (4)
 ★
★ ★
★ ★
★
