144 クルースニク、襲来!
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新
[1] [2] [3] [4] [メモ/メモ履歴] / 発言欄へ

【独】 変わり者 アレクシス > 【秘】 修道騎士 バルタザール
私がこれからすることを、貴方が知っているとでも?
[皮肉を交えた声が、バルタザールにだけ届く大きさで発せられる。]
そもそも、止められるものではありません。
――邪魔をするなら、貴方も私の敵です。
[生まれたばかりの赤子に、本人が望むかも分からない、増してや野茨公すら望まないであろう、自分勝手な願いを託した。
そのことに浮かんだ罪悪感はあれど、これからの行動には一片の迷いもない。
冷えた瞳がバルタザールを見下ろし、鋭く言い放つ。]

【独】 修道騎士 バルタザール > 【秘】 変わり者 アレクシス
――知らん。
[「敵」と口にした青年に、苛立ちを籠めて吐き捨てた。]
だが、貴様が真にやり遂げようと望むことを、私が止めると思うのか。
[心が流れるのは、血を与えられた時の刷り込みの所為だろうか。
であっても、修道騎士であった頃なら、ソマリにそうしたであろうように、この青年にもそうするだけだ。]

【独】 修道騎士 バルタザール > 【秘】 変わり者 アレクシス
[口中に嫌なざらつきがある。
青年から離れると、それは更にじりじりと神経を灼く焦燥に変わる。
衝動に任せたなら、青年に飛び掛ってその首筋に思い切り牙を沈めただろう。
だが、それら一切を押し殺し、最後に一言だけ告げる。]
……―― 感謝する。
[おそらくは死地に赴こうとする、仮母に手向ける、別離の言葉を。]
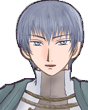
修道騎士 バルタザール
……ユーリエ。
[一歩そちらに向けて足を踏み出し、記憶を確かめるように名を呼ぶ。
修道騎士だった男は、全身が乾いた血で赤黒く染まり、死者の如き姿を晒していた。
大きく胸部を破損した銀鎧は、燻したように黒ずみ、聖性を思わせる鈍い輝きを失っていた。]

【独】 変わり者 アレクシス > 【秘】 修道騎士 バルタザール
[血の繋がりが、バルタザールの感情に呼応する。
拗ねた仕草、吐き捨てられた苛立ち。
誰かとの関わりを知らぬ男は、そこでようやく彼の心に思い至った。]
知っても尚、邪魔をしないのですねぇ。
そう来るとは思いませんでした。
[伝わるはずがないと、知ったのなら邪魔をするのだろうと、いつだって敵しかいなかった男には、その考えしかなかった。
目を瞬かせて、音にした言葉を噛みしめるように呟く。
そして穏やかに柔らかに、微笑みを浮かべた。]

【独】 変わり者 アレクシス > 【秘】 修道騎士 バルタザール
バルタザール、ギィの子、魔に染まった騎士――私の、
わたし、の……、
[彼は自身にとっての何だろう。
少なくとも、敵ではないことは分かった。
それだけ分かれば十分だと、そっと目を閉じ、暖かな別離の言葉を受け取る。]
貴方の選ぶ道の先に、幸福がありますように。
[男にしては珍しく、とても素直に彼の未来を願った。
それは先程まで繰り返した己のための祈りではなく、目の前の、血を分けた男のためだけに紡ぐ音色だ。]

修道騎士 バルタザール
[「私の知っているバルタザール」。
聖女の拒絶の言葉に、男は不思議そうに目を細めた。
そして、聖女の咎める視線の先を辿り、「兄」に当たる銀髪の青年を見遣る。]

【独】 修道騎士 バルタザール
[不意に浮上する記憶の断片。
――そう言えば。
頼まれていた。
などと、思い出していた。
あの時は、瀕死とて、敵の言ということもあり、しかと考える余裕などなかったのだが]

修道騎士 バルタザール
[視線は叫ぶアデルへ移った。>>196
ゆっくりと身体ごと向き直る。
そうして、修道騎士であった頃ならば絶対にしなかったであろうことをやった。
――笑ったのだ。]

修道騎士 バルタザール
アデル――アデル。
[揶揄の響きこめて、歌うように名を呼ぶ。]
ギィに血を供したのだろう?
望んで魔物に随従して、
今更何を聖女に弁明する?

修道騎士 バルタザール
[幼子の如くいやいやをする聖女>>204を流し目に見る。
その眼差しの、温かみの欠片もない冷厳さだけは、かつてのバルタザールと同一だった。]

修道騎士 バルタザール
[不意の問い。
こちらを見上げる聖女の瞳は澄んだ琥珀をしていた。]
私は、
[修復された男は、自らの内側を探る。
神、と言う単語が浮かんだが、形骸と化した思い出に、その信仰の拠って立つ感情が想起されないのだった。
沈淪の裡に掬い取ったのは、揺籃に繰り返し囁かれた言葉。最初の血を与えてくれた乳母の青年の冀求 。
その
ギィを守る為に在る。
私は彼の剣、
切り裂き、突き立ち、折れるを厭わぬ、ひとふりの剣だ。
[かつて神への信仰を告白したと同じ声、同じ表情で、今はギィへの忠節を語る。]

修道騎士 バルタザール
[まるで、「神」の中身が「ギィの守護」へとそっくり入れ替わったようだった。
剣として形づくられた男は、自らを支える信仰がなければ、瓦解してしまうほど脆い。
そのことに、果たして何人が気付いていたか。]

【独】 修道騎士 バルタザール
[正確には、
ギィに対して忠誠心があるかといわれれば、
定かではない。
誕生前に血親が灰化してしまったために、対面したことがないからだ。]

修道騎士 バルタザール
[駆け逃げるユーリエの後ろ姿を、その場に立ち尽くし眺めた。
随分と経った後に、おもむろに後を追うように階段を降り始めた。]
……そう言えば。
[と何気ない口調で語り始める、]
ギィから頼まれたことがある。
自分の子に形見を渡してくれと。
[ジークムントを振り返りもせず、歩を進める。]

修道騎士 バルタザール
― 三階へ続く階段 ―
[がしゃりと具足を鳴らし、破壊された石段を律儀に一段ずつ降りる。
決して急いてはいない。]
それ以上は覚えていない。
私には、何を託されたのか分からないのだ。
[最下段で一度だけ足を止め、]
……ただ、遺していくことを気にしていた。
[それだけを告げると、もう省みることはない。
聖女の痕跡を追い、疾駆を始めた。]

修道騎士 バルタザール
[疾走に移る前に、床に転がっていた剣を拾い上げる。
ギィの血を吸った剣は、彼が灰化した際に、踊り場から転がり落ちていた。
握れば、刃からチリチリと熱気に似た不快な気が発せられているのを感じるが、バルタザールはそれを無視した。
聖別銀の刃は、魔血に浸された血曇りで輝きこそ減じていたが、今でも魔に対しては充分に強力な武器であることに変わりはない。
握りこそ革が巻いてあるが、銀にダメージを受ける魔物なら、手に取ることさえ避けるであろう。
にも拘らず、男は愛用の武器であったそれを、躊躇いもなく手にした。]

修道騎士 バルタザール
[走り来る騎士は、地を這うような前傾姿勢、さながら走駆する獣か影のよう。
ふたりを前に制動を掛けるも、慣性を殺し切れず、盛大に灰と礫を蹴立ててもんどり打つ。
舞い上がる灰の煙幕の中から、やがてゆらりと人影が立ち上がった。]

修道騎士 バルタザール
[男は己に向けられた剣>>271を知覚する。]
……ソマリ。
[聖女を背に庇い、満身創痍に拘らず、聖騎士然として立つ男。
ああ、いつも奴はそうだった、と不思議な感慨が湧き上がる。]
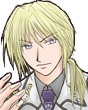
【独】 聖将軍 ソマリ > 【秘】 修道騎士 バルタザール
[彼の強さが信仰に基づくものだとは気付いていた。
一本の芯を通して、生き様を見せる。
自身の知るバルタザールと言う男はそう言う男だった。
危なっかしい男だと思っていた。
聖将の名を背負っても、
人を変えるのは神ではなく人なのだと信念を持つ身。
言辞を弄して、と告げられた言葉を未だ覚えている。
彼は実際のところ、身に染みる感化に甘いとも。
だから、敢えていつもはぐらかした。
神の為でなく、野茨公の為ではなく、誰が為でなく。
自身が為に戦う彼を、いつか見てみたかったから。]

修道騎士 バルタザール
当然だ。
私は剣、
何を斬るに躊躇いなどない。
[僅か数刻前に城主ギィへ宣りしたと同じ言葉を、今度はともに向かって言い放つ。]

修道騎士 バルタザール
[いっそ晴れやかな笑いを浮かべて、抜き身の剣を掲げる。
上段から真っ向から打ち割る、剛剣を。]
さあ、私を倒してみせろ!ソマリ!!
[そのうちで、痛みの蔓が頭蓋の内を這い伸びていく、]

【赤】 修道騎士 バルタザール
[心臓からしたたる血のしずくで綴られた言の葉が、「愛」を語る。
「愛」の意味すら知らぬ何ものかは、
「愛」の何たるかを知らぬままに、
乾いた大地が慈雨を吸い込むように、無心に耳を傾けた。]
[1] [2] [3] [4] [メモ/メモ履歴] / 発言欄へ
情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新



 フィルタ
フィルタ
生存者 (4)
 ★
★ ★
★ ★
★ ★
★犠牲者 (7)
 ★
★ ★
★ ★
★


