5 Chant 〜あなたと出会い生をうけ〜 SIDE:A
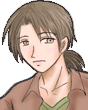
【赤】 士官候補生 ダーフィト
[ごしごし、と裾で額を拭われ、ぱちぱちと目を瞬いた。子供みたいだ。
促されるままに腰かけ、阿呆みたいに彼を眺める。
傍らの温もりがもそりと身じろいだ。
白い毛皮が、暗闇にぼんやりと光っている。
待っていろ、と言った彼が、瓶とカップを手にして戻ってきた。
渡されたコップはひんやりと冷たく、
注がれる液体は、白く濁っていた。
くんくん、と匂いを嗅いで、口に含んでみる。
爽やかな酸味が口内に拡がり、思ったより飲みやすい]
(*37) 2013/05/31(Fri) 22:58:06 (momo1126)
