192 G717村再戦十次会〜ラ神盤と行く!すごろクルーズ〜
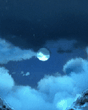
【独】 オレだよ、オレオレ > 【秘】 極楽蜻蛉 バルタザール
[尋ねる前に薄々勘付いてはいたが。それでも、声という音を伴い届く感情は確かに胸をざわつかせた。恐れる関わりを深く受け入れようとしていることへの警告が、頭の中で警報ブザーのようにけたたましく鳴り響き、止まない。――けれど。
縫い付けられたかと思う程重い唇をようやく開き、言葉を絞り出した]
――……そう、かね。
全く……最初から、こちらの目先に君が飛び込んできているのだろう。
敢えて視界から外す気もそうする理由もこちらにはないよ。
映していたいのでな。
[こちらへ真っ直ぐ向けられた双眸と、視線を合わせ。
声色を僅かばかり変調させた]
では目に映っていれば……それだけで満足なのかね?
私は少しばかり、物足りないのだがね――
[心の奥を探りたい思いの具現か、とうとうこちらから手を伸ばして。
頭に触れれば髪を梳くような動作で流すように撫でただろうか]
(-140) 2014/05/21(Wed) 20:02:29
