215 龍海乱舞 ─南方海域波乱航─
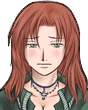
水破の精霊師 ガートルード
[ディークが死んでいたかもしれないという恐怖に、常の振る舞いを忘れてしまって。
宥めるように撫でてくれる手に、引き寄せられた胸元に顔を押し付けて泣きじゃくりながら、ひっそりと懐かしさを感じていた。
男の子の真似事を始めた後も、暫くはガートルードを良く思わぬ大人達の言葉の棘は収まらなかった。
義両親も義兄も、自分が言われた事を伝えたとき酷く辛そうな顔をしていたから、また言われたなんて言えなくて。
一人でこっそり隠れて泣いている所を見つかった時も、ディークはこうして、慰めてくれた。
今も、一方的に理不尽に喚く自分を宥めよう、落ち着けようとしてくれているディークに気付くと、段々落ち着きと共に申し訳なさが胸に湧いて]
…ごめん。
取り乱した。
(222) 2014/07/16(Wed) 20:59:46 (nadia)
