144 クルースニク、襲来!
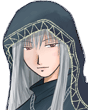
吸血鬼 シメオン
―サロンへと向かう廊下―
[>>151聖母の如き笑みと共に返ってきた言葉には、顰め面をした後に]
―それはそれは。
愚かな民草出身の俺などには身に余る光栄です、お母様。
[この親の事、どうせ言葉遊びのようなものだろうと判じ、棘のある視線と共に慇懃無礼な態度でお返しする。
絶世の美女と称される血親の貌に浮かんだ束の間の微笑みはその時にはとっくに消えていただろう。
綺麗だとは思うが、それ以上の感情は抱かない。]
……。
[分かっているなら聞くなと無言で応じる。
けれど愉快そうな響きを感じれば僅かに鼻を鳴らした。
理解してはいるのだ。――自分はこの血親に枷を付けられているという事を。]
(198) 2014/02/17(Mon) 21:54:16
