467 【SF人狼騒動RP村】 Sleeping Silver Sheep② ~愛はさだめか、さだめは死か~
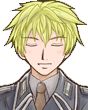
警備部 カレル
[どうしようもなく、消えてしまいたくて。
呼吸するのさえ、苦しくてたまらなくて。
ただただ、心臓から透明な血を流すことしかできなかったあの時、
その指先は、たしかにひとつの救いのようで…。
警備員に見つかりそうになり、
このままだと、彼女のお店にも迷惑をかける可能性に思い当って。
『ごめんなさい…』と、
諦めきった眼差しで店を出ようとした少女に、
彼女はたしか、一輪の花をくれたのだったか。]
(189) 2017/01/17(Tue) 00:09:30
