184 吸血鬼の共存試験
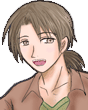
ダーフィト
[がさりと物音がしてもしやとそちらに目をやると、足音に怯えたように白い野兎が駆けていくのが見えた]
…あれ…
[自らの喉に手を当てる。白い丸い姿を目で追うとすぐに見えなくなったけれど]
……。
[気がついた――喉が、渇いている?気がつけば、何故今まで気付かなかったのかが不思議な程に。耳をすますけれど小川のようなものはないようだった。
やけにひりつく喉を押さえて歩くけれど、意識すればゆびさきは冷えて歩みは遅くなる。最早館に戻ることも叶わず]
(あ、これやばい、かもしれない…?)
[そんな気がだんだんと強くなる。月の位置は最初に見た時よりもずいぶんと低くなっており――夜明けは、いつくるのだろう。けして詳しくはないが、吸血鬼ならば太陽の光に弱い筈。
視線の先をずっと遠くに向ける。先に森に入った筈の彼は、ちゃんと館に戻れているのだろうか――]
(175) 2014/05/05(Mon) 19:20:53
