144 クルースニク、襲来!
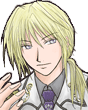
聖将軍 ソマリ
[支えを借りながらも、柔らかく腕は彼女を抱いていた。
聖将と謳われた男が、魔物の肩を借りるという皮肉げな姿は、
それでも何故か寄り添うに似ていた。
影に誘導されて至った場にて、彼に告げた己の言の葉。
それがどれ程の重さと、背徳に塗られているか、
信仰厚い教会が聞けば、蒼白となっただろう。
だが、生憎、自分は余り神を信じていなかった。
強いて言えば、聖女の言葉が一つ、強く残っていたが、
子供を言い訳にする心算など到底なかった。]
(171) 2014/02/26(Wed) 21:06:24 (momoten)
