497 堕天の服従試験
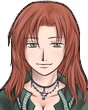
蛇 ガートルード
[最初、花園に紛れるごく小さな黒い染みのごとく認める蛇は、距離を近づくほどにその体躯を大きく感じられただろう。
天使がその傍に辿り着く頃には、
仔山羊よりも、天馬よりも、人の子よりも、遥かに
花だまりに臥して翼を小さく畳んだ、まるで龍種ほどの大きさで]
……
[瞬きをしない蛇の目は、確かに智性が宿るもの。
丁度若菜の色を映したかのような薄い緑が天使を向いて、こうべをその前に差し出した。
額から伸びて後ろへと曲がり流れる赤い角は、この時は片方だけ。
もう一方の優美な形は、根元近くで断ち折らればかりのよう、濡れた断面を晒していた*]
(138) 2018/03/19(Mon) 20:53:03
