178 薄暮の海―CLASSIFIED MISSION―
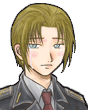
参謀 リヒャルト
――…ごめん、ごめんね。
泣くつもりなんて、ないのに……。
[意識しても震える心が涙を止めてはくれなくて
微かな嗚咽まじりの声を少年へと向ける。
初めて会うはずの彼が懐かしく、
ずっと逢いたかった、と思えてしまう。
彼の呼ぶ名は間違えるはずもない少女自身のもので]
如何して、私の名前――…
[知ってるの、と続けようとすれば、
足元で行儀よくお座りする愛犬が一つ吠えた。]
(124) 2014/05/05(Mon) 23:27:23 (renka)
