270 【誰歓】恋人爆発!クリスマス村!
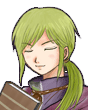
観測者 アデル
-回想・とある年のクリスマスイヴ-
[雪兎を手に持って歩く1つの姿が向かうのは花屋
誰へのお祝いとかではない、寧ろ彼自身の記念として
どんよりと重い空とは対照的に彼の気持ちはずっとずっと明るかった
もういい年しているのに、と自分でも思うが作りたかったものは仕方がない
手袋をして作った為に少々歪んでいるが、何かは十分理解出来るものだった
それを店先に置けばじゃあねと声をかけて
扉を開けると鈴の鳴る音と同時に椅子が音を立てる
ここは彼の家ではないけれど大切な彼の居場所だった
2人が待っていた事が嬉しくて、自然と笑みが零れる]
ただいま。
[彼は一切試験の結果を伝えなかった
その言葉の方が結果を伝えるよりずっといいと思ったし、自然だったから]
(115) 2014/10/31(Fri) 18:17:22 (Penia)
