270 【誰歓】恋人爆発!クリスマス村!
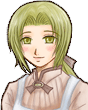
花屋 オクタヴィア
わぁぁ……
[そのお店の前で、その雰囲気に目をキラキラさせる。人並みに憧れは持っていたものの、それはあくまで現実味を帯びたものではなかったから。
ある冬の日。出掛ける、という言葉にはぁい、といつものように支度をすれば、彼が連れてきてくれたのは一軒の宝石店。装飾品など普段身につけることのない自分には足を運ぶことのないところで。
無言で彼を見上げれば、いいの?と言うように首を傾げる。その顔は緊張のためか口を真一文字に結んでいるが、目が輝いて頬が蒸気している──美味しそうなお菓子を目の前にする時の目だ。
手を引かれてお店に入れば、ショーケースに駆け寄り、指輪を見つめる。店員さんが一つずつ出し、並べてくれるのを手に取り、眺める──]
(98) 2014/10/31(Fri) 00:16:24 (*さとこ*)
