477 【R18完RP村】暁天はかく語りき、
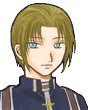
【2】尚書官長補佐 リヒャルト
[騒がしいはずのこの場に耳に一番届くのは心音だった。
彼は歯を噛み締め、弟の王子様に跪く婚約者を見ている。
嘘はぬかるみのようにどんどんと己を沈めていくのに彼は気づいただろうか。
すがっていたはずの姿から発せられた言葉に微かに眉をしかめる]
第一王子までこの文書を偽造の可能性があると仰るのですか。
我々が証人でこの御名玉璽――、
国王陛下のご遺志でございます。
この文書を疑うということは国王陛下のご遺志をお疑いになることになりましょう。
[尚書長官から肩を叩かれれば、彼は息をのんだ。
肩から伝わる重みと一部の文官や元老院の面々の顔を見れば、
薄暗い貴族社会を見てきた彼ならすぐに理解ができた。
"なにか"があったのだろうけど、
王様に国璽があるのならば彼はそれを疑う気持ちは持てなかった]
(82) 2017/04/21(Fri) 16:48:06
