297 吸血鬼の脱出ゲーム
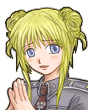
碧眼 シルキー
――馬鹿だな、お前。本当に馬鹿だ。
[己の内に血が満ちる感覚を味わいながら、青年は蔦をバルコニー全体へと広げて、彼と狐を守るように配置した。
そして、ぐったりと眠る狐を抱え上げ、膝の上へと横たえた。]
なぁ、いい加減、面倒くさいだろう?
こんなガキを背負うのは。
[親指で狐の目元を優しく撫でてやりながら話しかける。
いつか友人であった彼女がやってくれたように。]
――良いんだぜ。
お前が居なくなってからずっとひとりだったんだから。
「壊れてしまう」だなんて、泣きべそかいて言ったけど。
きっと、平気なんだ。痛みはそのうち薄れるから。
[低く抑えた声は、バルコニーを浸してゆく。]
(79) 2015/02/04(Wed) 16:56:30
