297 吸血鬼の脱出ゲーム
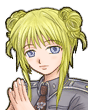
碧眼 シルキー
―中庭―
[――どれほどの時が経ったのか定かでない。永劫にも等しい時間だった気もするが、一瞬だと言われればそうと納得もできる。
青年は青玉の瞳をそっと開く。
右手には手折った杜若、左手は心の臓の上で握りしめられていた。
握った拳を開いてみれば、傷一つなく白磁のように美しくはあるものの、今までよりも骨ばった力強い掌がそこにはあった。]
……行こうか。彼女が待ってる。
[その声は滑らかで冷たいテノール。
今の状況を不思議に思う素振りもなく、青年は立ち上がる。
少しだけ乾いた唇を舐めるその舌は赤く、蠱惑的に揺らめいた。]
(60) 2015/01/31(Sat) 01:01:17
