383 【SF人狼騒動RP村】 Sleeping Silver Sheep 〜 猫と兎も 勘定に入れません 〜
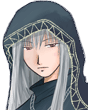
聴く人 シメオン
私は、増してこの男も――お前の望みに応えられる者ではないだろう。
[その透明な蓋の下、赤い髪の面影を辿るように、手のひらが幻の頬を撫でた。]
科学技術を憎む、と、お前は言っていたか。
語られぬことを、知ることはないが。
お前も、絶やされゆく者で、あったのだろうか。
お前の故郷も、美しかったのだろうか。
地に息づいていた者たちの、いかに多くが、後より現れた物に、絶やされたことだろう。
けれどそれは、人の手に限らず、繰り返されてきたことのように、思う。
その“術”に、正否を断ずることは、私には出来ない。
それもいずれ、あめつちの間にあるものから、できているのだから。
作り出した者たちが、自らに問い、負うべきことと。
けれど――…
(59) 2015/10/23(Fri) 00:41:39
