502 温室世界の住人たち
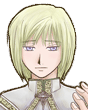
司書 ファミル
[カウンターに『隣にいます、急ぎの用はそちらへ』と書かれたボードを置いて、自宅へと戻る。
扉を開けてすぐに包み込んで来るのは甘いあまい、花の香。
その源をたどれば目に入るのは雪色の花。
細い花弁を重ねた様は一見繊細にも見えるが、茎には目立たない棘が連なっている。
己が本体の写しと言われるそれを一瞥した司書は、奥の棚から地下の探索に必要そうなものを取り出して鞄に詰めた後、ゆっくりと通りに出て]
……あ。
食事。
[すっかり忘れていたそれをどうすべきか。
そんな思考に囚われて、その場に足を止めた。*]
(28) 2018/06/18(Mon) 23:31:58
