84 【お祭り騒ぎ】使い魔たちのハロウィン・パーティー【飛び入り歓迎】
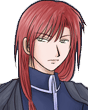
ストリゲス ギィ
[窓ガラスに映らない鴉は氷の精が描いた絵を横目で眺め、黒づくめが丸まっている横を首を傾げて通り過ぎる。
ソファの上で笑っている少女には剣呑なものを感じて視線を送った。それはたとえば、猛禽の匂いを嗅いだとかそういうこと。
白い少女が目に貯めた涙を嘴 唇で啄もうとして途中でやめ、妙に物言いに年季が入った黒衣の娘をじっと見つめる。
が、それも騒がしい奴が走り回ってテーブルに手を乗せたのに気を取られた。
注意しようと近づいた向こうに、いつか見た顔を見つけてさらに気が逸れる。]
(20) 2013/10/27(Sun) 21:23:07
