498 豊穣の村 ―人狼BBS風の少人数人狼騒動RP村―
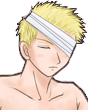
【秘】 負傷兵 シモン > ならず者 ディーター
[仲間が近付いても、眠ったようなその男は目を開けない。
左目も、そのはずだった。
だが気配>>132にぐわりと目を見開いた。
自分をこんな風にした人間の怨念、憎悪を
糧に生き続けたこの左目は、すでに彼らとすら
違うものへと成り果てているのかもしれない。
それでも仲間が手を差し伸べるなら。
言葉が届かなくても嘗ての約束通り
連れて行ってくれると信じた左目は喜ぶだろう。
濁った瞳孔が意思を見せるように収縮し
その目に仲間を映し続けるのだ**]
(_29) 2018/04/30(Mon) 00:55:31
